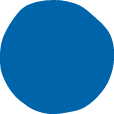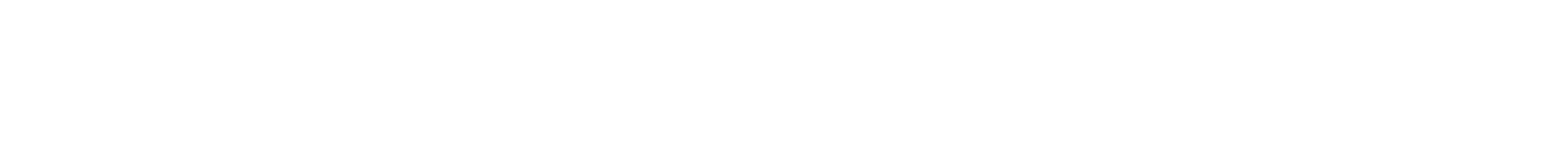-2026年
-2025年
人材不足を考える

最近、「人がいない」「ドライバーがいない」という言葉をよく耳にします。
とはいえ、若い人の応募もあるし、女性の応募者も増えています。
でも、運送業をやっている僕からすると、「人がいない」というよりも、「人を乗せるトラックが、もう買えないんですよ」というのが本音だったり、業務内容が「運送会社ってこうだから」というのが障壁になっていたりするのかなあ・・・と。
先ずはトラックの価格。
数年前までは、10トンの冷凍車でも2,000万円くらいで買えていました。
それが今は、3,000万円近い金額になっています。
トレーラーヘッドにしても、新車なら1台3,000万円級。
冷凍シャーシは、新車で2,000万円近く、中古でも似たような価格。
「ちょっと頑張って買いましょうか」というレベルでは、もうないんです。
さらに、燃料、保険、整備費、部品代…すべてが上がっているのに、
運賃はそこまで上がっていない。
経費は増えて、粗利は減る。
そんな中で「人が足りない」と言われても、じゃあ「誰をどの車に乗せるの?」 「どんな仕事をさせるの?」という話になる。
正直なところ、人材は来てるんです。
「働きたいです」という人もいる。
でも、乗せる車がない。条件に合う仕事がない。だから雇えない。
これって、「人材不足」と言えるのかな?と思ってしまいます。
「人が集まらない」 「定着しない」と言われる会社には、
・古くて壊れやすい車
・待機ばかりのスケジュール
・過酷な荷役
そんな現場が多かったりします。
でも、原因をたどっていくと、やっぱりそこには
「車を更新できない」 「運送会社の仕事ってこれという従来の概念」という事実がある。
わかるんです。
運送会社って、物理的な問題を解決する仕事なので。
時間や労力などが簡単に短縮できない、楽に出来ない事も。
とはいえ、このままでは、採用も育成も、全部が手詰まりになります。運送業界の“人手不足”は、単なる人の問題じゃない。
設備、仕組み、そして経営体力の問題。
それをごまかさずに見て、変えていく覚悟がないと、
この先、会社を続けていくこと自体が難しくなるかもしれません。
「人がいない」という言葉の裏に、何が隠れているのか?
本当に見ないといけないのは、「人」ではなく、「人を活かす道具や環境を用意できるかどうか」。
僕は今、それを真剣に考えています。(考えるのはただなので)