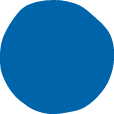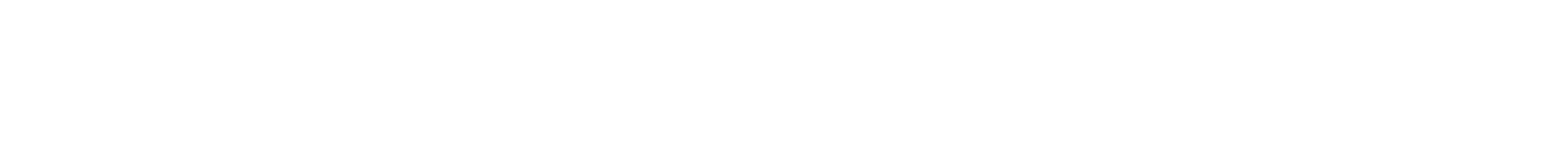-2026年
-2025年
オイディプス王が「普通に見えてしまった」話

オイディプス王の話をあらためて整理してみて、
正直、最初に浮かんだ感想はこれだった。
「……これ、普通の話じゃない?」
国のために原因を調べ、
自分が原因かもしれないと薄々わかりつつも調査をやめず、
真実を突き止め、
最後は王を降りることで責任を取る。
江戸時代の時代小説や、清廉な武士の話なら、
わりとよく出てくる展開だと思った。
だから一瞬、
「これが教養になるほど特別な話なのか?」
と感じた。
でも、そこで止まらなかった。
よく考えると、
オイディプスは悪意があったわけでも、
判断を間違えたわけでもない。
むしろ彼は一貫して、
「正しいと思われる選択」しかしていない。
それでも破滅している。
ここが、日本の時代劇や武士道の物語と決定的に違うところだ。
日本的な物語では、
筋を通せば、どこかで意味が回収される。
たとえ切腹して終わったとしても、
物語としては「整う」。
ところがオイディプス王には、
悪者がいない。
不正もない。
筋も通っている。
それでも、
世界は壊れたまま終わる。
このとき、はっきり気づいた。
オイディプス王が「普通に見えてしまった」のは、
自分がすでに
「正しくやっても、どうにもならない世界」
を生きているからなんだと。
誠実に考えても、
原因を突き止めても、
それで状況が良くなるとは限らない。
経営でも、人間関係でも、
構造そのものが限界を迎えている場面では、
そういうことが普通に起きる。
だからこの物語を読んで、
「うわ、きつい話だな」とはならず、
「ああ、あるよね。こういうこと」
と感じてしまった。
オイディプス王が教養になる理由は、
話が立派だからでも、
覚悟が美しいからでもない。
正しく生きても破滅する世界を、
はじめて真正面から描いた物語だからだと思う。
彼は世界を救えなかったし、
物語をきれいにも終わらせなかった。
それでも、
真実を隠さず、
嘘の秩序を終わらせ、
主役の席を降りた。
その振る舞いだけが残った。
正しさが通用しない世界で、
それでも人はどう振る舞うのか。
この物語は、
その問いの原型なんだと思う。