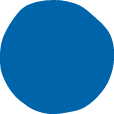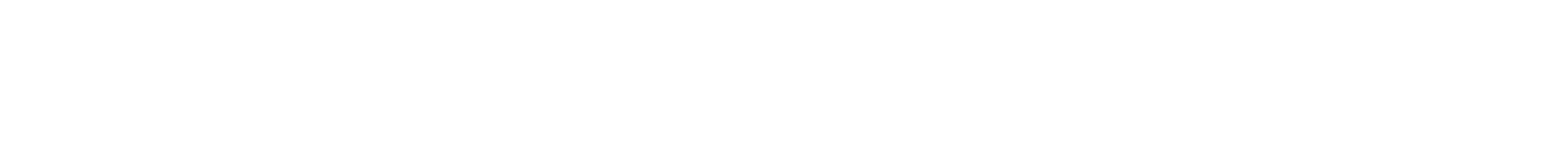-2026年
-2025年
まあまあ、すごい事になってるんだなあ・・・

朝のニュースで、「全国学力テストの数学、正答率が50%を下回った」と聞いて、思わず「終わってますわ…」とつぶやいてしまいました。
しかも、その流れで「ソロバン回帰を検討?」なんて話まで出ていて、なんだかズレてるなぁ…と。
もちろん、ソロバンに意味がないとは思いません。
むしろ、僕も小さい頃にはそろばん塾に通ってましたし、今でも“数字の感覚”を養うには優れたツールだと思っています。
でも、今の子どもたちがつまずいているのは、「計算が遅いから」じゃない。
“考える力”そのものが弱くなっているんですよね。
問題文の意味がわからない。
状況がイメージできない。
どう考えていいのか、そもそもピンとこない。
つまり、ソロバンの話じゃなくて、考える時間や経験が、根本的に足りてないんです。
子どもたちの思考力の低下の裏には、
大人たちの“焦り”がある気がしています。
「すぐに答えを出せ」
「正解はこれだ」
「間違えたらダメ」
「調べたら出てくるでしょ」
…こんな空気の中で、「じっくり考える」なんて無理な話ですよね。
スマホで何でも答えが出る時代だからこそ、“わからない”ことに耐える力とか、
“どう考えるか”を楽しむ感覚が、ますます大事になってきているのに。
本当に必要なのは、
「計算の速さ」や「点数の高さ」じゃなくて――
- 自分で問いを立てられること
- 人の意見を聞いて、自分の中で咀嚼できること
- わからないことを、粘り強く考え続けられること
そんな**“深く考える力”**が、これからの時代を生きる子たちにとって、最も大きな財産になると思うんです。
そしてそれを育てるには、**時間と余白、そして“失敗してもいい空気”**が絶対に必要。
つまり、大人の側が「焦らずに待つ力」を持たないといけないんですよね。
ソロバンの話もいいけれど――
その前にまず、「子どもが考えることを、僕ら大人がどれだけ許せているか?」
ここに立ち返ることが必要なんじゃないかと思った朝でした。
学力テストの点数よりも、
**“思考する経験の総量”**を大切にしたいですね。
それが、未来の社会をちゃんと生き抜いていける子どもたちを育てる、一番の土台になると信じています。
では、今日もぼちぼち、いきましょう。